
資金繰り管理(初歩)
従業員にとって一番大切なことは会社が安定的に存続し続ける存在であること。
そのために会社の資金が効率的に回っていることが重要になります。
TNC「お金の使い方」チーム担当の脇本です。
4月になり一斉に新社会人を迎える時期となりました。
私の社会人のスタートは銀行員でした。30数年前を懐かしく思います。
「中小企業の育成発展に貢献したい」という思いをもって入社し、12年少しの期間でしたが、内容の濃い法人融資営業、審査部門での業務に携わることができました。
この間に財務分析、資金繰り分析を徹底的に叩き込まれ、自身も勉強、研究したことがその後の財務コンサルとしての企業支援や現在の実務にも役に立っています。
今回は資金繰り管理について簡単な考え方をお伝えしたいと思います。
会社では決算書があり、利益が出ている=黒字、損失を計上してしまった=赤字ということは明確にわかります。
でも実際に資金繰りが回っているか、決算の数値以上にいいのか悪いのかは、また別の話となります。
つまり、利益が出ていても資金繰りが厳しいこともありますし、逆に赤字でも資金的に余裕がある場合もあります。
なぜそんなことが起きるのか。
それを知るためには、お金に色を付けて管理をすることです。
と言っても、実際に紙幣に色を塗るわけではありません。
入ってくるお金、出ていくお金をカテゴリー分けをするのです。
なーんだ、そんな簡単なことかと思われたかと思います。
でも、これを行うことで劇的に資金の見え方は変わります。
逆を言えば、こんな簡単なことなので誰でもできます。
簡単すぎてしている人も少ないかもしれませんが、しっかりと管理することで現状分析と将来の資金繰り予想、計画も立てやすくなり、先々の資金的な不安も払拭されるのです。
しないより、絶対にした方がいいと思います。
これには特に決まりがあるわけではありません。あくまで私のやり方です。
その方法とは、資金の入出金の項目を3項目に分けるということです。
その3項目とは
- 本業の業務にかかわる資金の出入り=入金の代表的的なもの:売上代金回収。支払の代表的なもの:仕入代金決済資金、人件費⇒【経常収支】
- 本業以外の資金の出入り=入金の代表的なもの:設備売却代金、消費税還付。支払の代表的なもの:設備購入代金支払い、税金支払い、配当金支払⇒【経常外収支】
- 金融機関など資本的資金の出入り=入金の代表的なもの:借入金、社債発行、出資金。支払の代表的なもの:借入金返済、社債償還⇒【財務収支】
これらの項目は企業会計原則などの規則に沿ったものではありません。
会社にとって、本業に関する資金の収支なのか、それ以外なのかを管理しやすいように分類するだけです。
それ以外の社外からの業務以外の資金収支=主に金融機関からの借入やその返済になるかと思いますが、これらを財務収支として管理します。財務収支については借りた時点で返済額も明確になりますので1年先ぐらいまではすぐに収支計画ができます。
これらを分けて実績管理することで何が原因で資金不足が発生しているのか、逆に資金余剰になっているのかが明確になっていきます。
*本業の収支がマイナスなのか⇒本業のやり方をテコ入れしないといけない
*本業以外の収支が足を引っ張っているのか⇒一過性なものか、経常的なものか
*財務収支が経常収支を上回っている⇒借入返済のピッチが早すぎる。折り返しの借入金調達をどのタイミングで依頼するか、借入返済のピッチを緩める交渉をする
先々で資金が必要なのか、調達せずに資金繰りが回っていくのか。
資金が必要な状況が見込まれるのであれば、前もって金融機関にもその原因を明確にしたうえで資金調達交渉ができます。
金融機関は急に「金を貸してくれ」と言われると、貸すことが本業でも二の足を踏んでしまいますが、資金計画を見せてもらった上で「、〇月に〇〇百万円必要なので検討してもらえないか」と言われると稟議申請もしやすくなります。
金融機関も資金を貸して商売しているのですから貸したいはず。
金融機関が貸しやすいように資料を整備することで円滑な資金調達もしやすくなります。
あくまで、目的は資金調達することではなく、実際の資金状況を把握することです。
これを徹底することで、安心して企業活動を行うことができるようになると思います。
(脇本裕正)


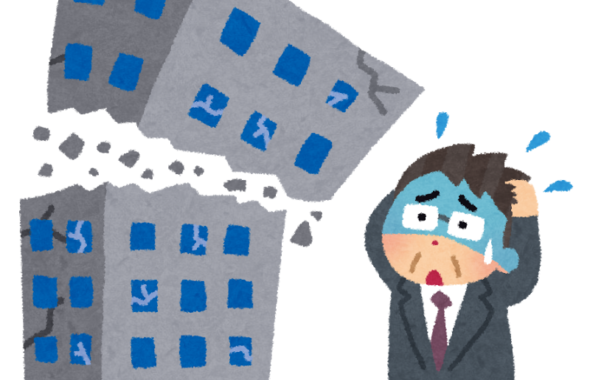





この記事へのコメントはありません。