
統合保育と母から学んだこと
皆さん、こんにちは。TNC人つくりチームの瀧幸子です。
私は、3人のこども(中2、中1、小1)のお母さんをしながら働いています。
約20年間、保育士として働く中、いろんな現場といろんな人たちと触れ合う中で感じたことは
今、かかわる「経営」や「人つくり」に繋がると思うことがよくあります。
私は、障害ある子も無い子も一緒に過ごす「統合保育」の実践を重ねてきました。
集団であそぶ時はあえて、できる子たちにあわせるのではなく「できない子たち」にスポットをあてた保育内容を大切にしてきました。
この実践は、できない誰かを一人にしなかったと思います。
できる子たちは、より工夫し、自分の発見を「伝える」ことも楽しんでいたのです。
クラスがチームだとしたら、できない子たちができる内容である為、どんどんまとまります。
例えば、乳幼児クラスでは、そのものの感触を楽しむことから始まり、子どもたちは何回も何回も同じことを繰り返します。
あそび方なんて無く、一人ひとりの表現があります。
こどもの枠を超え、おじいちゃんおばあちゃんたちにも喜ばれることをやってきました。
集団の中でこどもたちは共に育ちあうと思うのです。
保育というコミュニケーションの原点は、人です。
これは、TNCの理念・人つくりチームとして在り方を考える時、重なる部分がたくさんある気がするのです。
社会の環境や制度はどんどん変わっていきます。
情報がありすぎ、逆に孤立化が進む傾向にあるかもしれません。
その中で、私が大切にしたいものは、伝承されてきたあそびやカタチの無いもの(料理、音楽、絵画、アートetc.)だったりします。
時代を戻すといいますか…人は、そういうものこそ、自然にチームになっていくと思うのです。
連携しないと成り立たない、孤立していては成り立たないものだと考えます。
「統合保育」と「経営」
かけ離れているように見えますが、もしかしたら、かけ離れているもの同士が重なった時のほうが、変化していくスピードが早いかも!と思うのは、私だけでしょうか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
母はいつも私に「ごめんね」と言います。
普通はお母さんがしてあげることが、できないからだそうです。
私は「普通」がわからないのです。
比べるからそうなるのかもしれませんが、私にとってはどうでもいいこと。
生きていてくれてありがとうだけなのです。
母は、筋ジストロフィーという病と共に生きています。
そういえば、そうだった!という感覚。
母も、一人にしたくない存在です。
母が謝らなくていい社会をまわりの人たちと手を繋いで、つくりたいです。
人は、バランスをとれた人が元気なのかもしれないと、思ったりします。
凸凹は誰でもあると思うのです。
バランスをとれなくなった時、人はプツって、糸が切れてしまうような気がします。
子育てしながら働き続けてきた経験は、女性支援にかかわっていきたいという思いも、強くしていきました。
誰にも頼れない立場の人たちの状況を「自分のこととして」想うようになりました。
私は「働く」ということの意味を更に深く考えます。
これまで通ってきた道は、今の私が在るために、大切な大切な時期だったと感じます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。



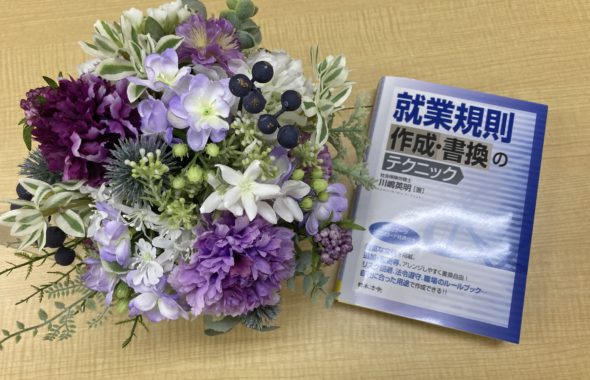

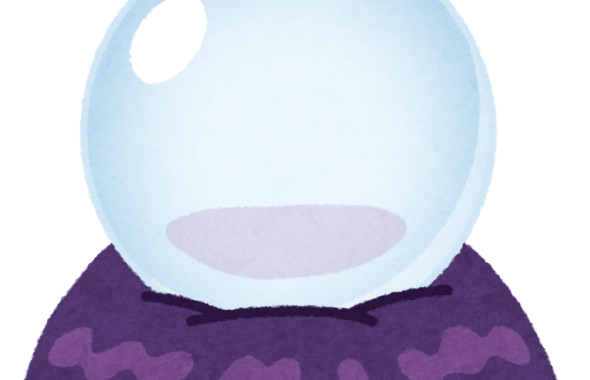


この記事へのコメントはありません。